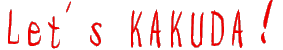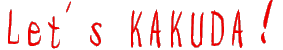2025/7/1UP
企業より起業
今月初め、厚生労働省が人口動態統計(概数)を公表しました。204年に生まれた子どもは68万6061人。統計開始以降初めて70万人を割り込みました。就職氷河期世代を中心とした経済的な課題。ライフスタイルの多様化。原因は多岐にわたると思います。国の将来の希望を持てず「子どもたちに申し訳ないから生まない」という考えもあるようです。
収入が増えれば多少は数字が上向くかもしれません。子育て支援策、出産応援などの政策も、少しばかりは刺激になるかもしれません。ですが、そもそもの話、婚姻者の減少が背景にありそうです。
こども家庭庁の資料を見ると、婚姻数は1972年の109万組がピーク。23年は47万組と、半数以下になっています。結婚と出産の相関性が強い日本において、影響は大きいと感じられます。
では、どうすれば婚姻数を増やせるのか。答えは分かりませんが、先ほどの資料に面白いデータがありました。「見合い婚」か「恋愛婚」かの統計で、近年新たに「ネット」が加わっています。直近では、想像通り恋愛婚が74・6%と最も高いのですが、次点はネット。15・2%と、見合い婚の9.9%を上回っていました。
なるほど、確かに最近の身の回りで結婚した人で「出会いはアプリ」「オンラインゲームで知り合った」との話が珍しくなくなりました。インターネットを通じた知り合い「ネッ友(とも)」を持つ子どもが多い時代。未来の婚活の中心はここになるのかもしれません。
最後に、地方においては、出生数・率と共に大きな課題として立ちはだかる「流出」についても触れたいと思います。
宮城県の人口流出は、仙台市の「支店経済」が要因―。他紙で恐縮ですが、先日、専門家による分析を紹介する記事が掲載されていました。
宮城県は、東京圏に本社がある事業所(=支店)の割合が全国で最も高く、必然的に、若者が就職する際は東京の大企業に就職してしまうとのこと。また、大学進学時の流出率の高さについても解説。仙台市は東北各県の若者を呼び込んでいるものの、結局は「東京への中継地」に過ぎないと指摘していました。
地方ほど民間企業の就職口が少なく、結果として、公務員人気の高さが目立つ印象です。地元に「十分な収入が見込める」仕事がたくさんあれば、流出を防ぐ効果を期待できます。
個人的には、工場誘致ではなく、地元を拠点とした企業が増えることが望ましいところ。なかなか難しいとは思いますが、たとえ小さくともどんどん起業する風土が生まれると、地域の持続性にもつながる気がします。城下町として栄えた角田。「起業城下町」を目指すのもいいかもしれませんね。
|
田植えを終えた市内の水田。
収穫時期が待ち遠しい。 |